
魚住洋一

中ハシ克シゲの"ZERO"──実寸の1/32大の零式艦上戦闘機のプラモデルを2×3mm平方ずつ接写、サービス判にプリントされた一万数千枚から二万数千枚の写真をつなぎ合わせ、実物大の零戦を復元。ひしゃげたかたちをそのまま展示し、最後には火を点けて焼却。1998年以来、そうした"ZERO Project"が何度も繰り返されてきた(右図 : ZERO #BII-124/the Aviation Heritage Center, Darwin, 2000) 。
中ハシの"ZERO Project"は、一つの旅。それは、大阪の地にはじまり、ブリスベーン、西宮へ、そしてダーウィン、さらに、2002年にはカウラへと至った一つの歩み。"ZERO"は、マス・メディアが"Kamikaze Attack!"と声高に叫んだあの"9.11"前後には、村上隆がキュウレートした"Superflat"展に加わり、合州国西海岸で展示されてもいた。日本、オーストラリア、そして、アメリカ合州国──中ハシの"ZERO"のそうした歩みが私たちに問いかけるのは、「戦争の記憶」──過去の、そして、現在の「戦争の記憶」ではなかろうか。
「いったい、あの映像〔="9.11"の映像〕にかつてない衝撃を受けたという者は・・・・それより遥かに"崇高"に見えさえもする"ヒロシマ・ナガサキ"のキノコ雲や、太平洋上で青い空を背景に自爆攻撃を展開する"カミカゼ"の信じがたい映像には同様の衝撃を受けることなく、なぜ"9月11日"に至ることができたのだろう?」と椹木野衣が書いていたことを、ふと思い出す(1)。──風化した戦争の記憶。ここ日本では、「戦後」とさえ語られなくなってすでに久しい。南北に分断された朝鮮半島や米軍基地を抱える沖縄では、また元従軍慰安婦など戦争被害者たちにとっては、まだ「あの戦争」は終わってはいないし、今なお「戦争」が「日常」でありつづけている人々が世界各地に居るというのに。
ここ日本における戦争の記憶のそうした風化は、おそらく中ハシにとっても他人事ではなかったはずである。たとえば彼はこう語っている。「戦争経験のない自分にとって、戦争といえば、子どものころ遊んだ零戦のプラモデルしかない。それに自分としてのリアリティがある。だからモチーフとして選んだ」と(2)。昭和30年代生まれの「戦後世代」中ハシ克シゲにとっても、「戦争」は椹木野衣のいう「漫画、アニメ、特撮、プラモ」の戦争というサブカルチャー化されたものでしかなかった。「漫画、アニメ、特撮、プラモ」によって再-現(re-present)された「戦争」──プラモデルの零戦を例に挙げれば、開戦当初、カーチスP40やグラマンF4Fワイルドキャットに速度や旋回性能においてはるかに上回っていた零戦の「カッコイイ」端整な形象に「戦争」の現実が摩り替えられ、そこからナショナリスティックな日本賛美の傾向が、プラモデルの零戦を買い求める中ハシのような少年たちの心に、密かに植え付けられていったのである。
そのことに中ハシはきわめて自覚的だったといえよう。彼がプラモデルの零戦の写真で"ZERO"を作ったのは、まさにそれゆえである。中ハシは、いくつかの"ZERO Project"で、零戦のエンジン音や射撃音を口三味線で流していたが、そのリアリティの欠如こそ、逆に中ハシにとっては戦争のリアリティそのものだったのである。
しかし、このことは、あらためて問い質(ただ)してみなければならない。
プラモデルの零戦の、しかも、その写真で"ZERO"を作り上げる、とはどういうことだろうか、と。
オリジナルのコピーでしかない、ちっぽけなプラスティックの玩具の零戦。そのプラモデルの零戦をさらにコピーした写真で作られる"ZERO"。──私たちのまえに展示されるのは、そうしたコピーのコピーにすぎない。まるで、オリジナルなど存在しなかったとでもいうかのように。

それは、たしかにそうにちがいない。「戦後日本」に生きる私たちの多くは、「戦争」から目を背け、それに直面しないままに済ませることができたのだから。──とはいうものの、中ハシの"ZERO"は、それがコピーのコピーであり、贋物の贋物であることを明確に示すことで、かえって、私たちが生きる「平和ボケ」の日常に痛烈な皮肉を浴びせる結果となる。米軍のアフガン侵攻やイラク侵攻がディズニーの娯楽映画『パール・ハーバー』の映像と同列化されてしまうような私たちの日常とはいったい何なのかを、中ハシの"ZERO"は問い質すのである。それを観る者に「暗さ」を感じさせない中ハシの"ZERO"は、その「明るさ」のために、逆に「暗さ」以上の「暗さ」を感じさせる場所へと私たちを導き入れてしまうのかもしれない。

中ハシの"ZERO"がこうした逆説的な「明るさ」を醸(かも)し出しているとすれば、彼がジュラルミンなどの金属で「構造体」としての零戦を作り上げたのではなく、写真によって「表層」だけの零戦を作り出したことも、それに大いに与っているのだろう。このことに触れて、彼はこう語っている。「タイトルの"![]() (ゼロ)"は、零戦のゼロ、数字の何もないという意味で空洞。0(ゼロ)が横になっているのは、ペチャンコな形状を表している。表層という意味もある。・・・・この作品は、構造からスタートするのではなく、表層からスタートしている。表層が"なしくずし"的に構造を作っていくことをしたかった。・・・・膨れていようが潰れていようがかまわなかった」(3)。写真をセロファンテープでつなぎ合わせたペラペラの"ZERO"、写し損なって一部穴が開いたり、構造がないために折れ曲がってペチャンコになってしまった"ZERO"。中ハシは、それを観る者に否応もなく、そこにあるのが贋物の表層だけの零戦であることをあからさまにする。そこにあるのは、零戦の抜け殻、まさに「数字の何もないという意味で空洞」でしかない。だからこそ、それを観る者は、まるで我が身の空洞を覗き見るような錯覚に陥るのである。村上隆は"Superflat"展の入口に中ハシの"ZERO"を配していたが(左図 : ZERO Type52/"Superflat"/Museum of Contenporary Arts, Los Angels, 2001)、それは彼によれば、「敗戦国日本、そのインポテンツな現在」を象徴させるためであったという(4)。天皇の戦争責任が不問に付され、「あの戦争」にもかかわらず、「昭和」という時代が「戦前」と「戦後」を貫いて続き、高度成長のなかで、まるで「戦争などなかった」と言わんばかりの風潮が蔓延(はびこ)っていった。高度成長期に植木均が歌った「無責任一代男」の歌詞──「とにかくこの世は無責任、こつこつやる奴ぁご苦労さん♪」──に象徴されるような(5)、丸山眞男のいわゆる「無責任の体系」が、ここ日本では「戦前」と「戦後」の表面的な断絶を越えて、いまなお続いているのである。まさにここにあるのは、「敗戦」の意識すら消去されてしまうような、村上のいう「敗戦国日本、そのインポテンツな現在」そのものであろう。
(ゼロ)"は、零戦のゼロ、数字の何もないという意味で空洞。0(ゼロ)が横になっているのは、ペチャンコな形状を表している。表層という意味もある。・・・・この作品は、構造からスタートするのではなく、表層からスタートしている。表層が"なしくずし"的に構造を作っていくことをしたかった。・・・・膨れていようが潰れていようがかまわなかった」(3)。写真をセロファンテープでつなぎ合わせたペラペラの"ZERO"、写し損なって一部穴が開いたり、構造がないために折れ曲がってペチャンコになってしまった"ZERO"。中ハシは、それを観る者に否応もなく、そこにあるのが贋物の表層だけの零戦であることをあからさまにする。そこにあるのは、零戦の抜け殻、まさに「数字の何もないという意味で空洞」でしかない。だからこそ、それを観る者は、まるで我が身の空洞を覗き見るような錯覚に陥るのである。村上隆は"Superflat"展の入口に中ハシの"ZERO"を配していたが(左図 : ZERO Type52/"Superflat"/Museum of Contenporary Arts, Los Angels, 2001)、それは彼によれば、「敗戦国日本、そのインポテンツな現在」を象徴させるためであったという(4)。天皇の戦争責任が不問に付され、「あの戦争」にもかかわらず、「昭和」という時代が「戦前」と「戦後」を貫いて続き、高度成長のなかで、まるで「戦争などなかった」と言わんばかりの風潮が蔓延(はびこ)っていった。高度成長期に植木均が歌った「無責任一代男」の歌詞──「とにかくこの世は無責任、こつこつやる奴ぁご苦労さん♪」──に象徴されるような(5)、丸山眞男のいわゆる「無責任の体系」が、ここ日本では「戦前」と「戦後」の表面的な断絶を越えて、いまなお続いているのである。まさにここにあるのは、「敗戦」の意識すら消去されてしまうような、村上のいう「敗戦国日本、そのインポテンツな現在」そのものであろう。
そういえば、中ハシは、"ZERO Project"を企画するようになった動機を、「戦争により戦前・戦後と二分化されている・・・・昭和をテーマとして、これから作品を作っていきたい。この"ZERO"がそのシリーズの最初の作品となる」と語っていた(6)。また、2000年に西宮市大谷記念美術館で開かれ、シリコンの巨大な菊の花に昭和天皇の等身大の黄金のブロンズ像を包み込んだ作品と"ZERO"を中心として展示された彼の個展、そして、2001年に米子と大阪のギャラリーで開かれ、ブロンズのままの彫像と金箔を施した彫像とからなる一対の昭和天皇像が展示された個展のタイトルは、ともに「あなたの時代」であった(7)(右図 : あなたの時代/「あなたの時代」/大阪、児玉画廊、2001)。「あなたの時代」とは、その英訳が"Your Majesty's Reign"であることからも知られるように、日本国の「国歌」とされる「君が代」の口語訳であり、中ハシはその言葉によって昭和天皇の治世を言い表そうとしたのである。彼が"ZERO Project"によって問いかけているのは、「あの戦争」への問いだけではなく、戦前から戦後へと連なる「昭和」への問いでもあったのである。
ところで、「彫刻家」を自称していたはずの中ハシが、"ZERO"において写真を手法として用いたというのは、どういうことだろうか。というのも、「表層」だけの写真には、伝統的な彫刻のもつ「ボリューム」や「深み」が決定的に欠落しているからである。


思い返してみると、「彫刻」への中ハシの思いは、きわめてアンビヴァレントなものだったのかもしれない。彼にとっては、彫刻とは「ボリューム」や「深み」という「量感を表現する芸術」にほかならず、そして彼には、それを目指そうとして挫折した経緯があったのである。80年代の半ば、彼は、「日本的なもの」としての松を、蝋型(ろうがた)鋳造により葉に至るまで鋳型で抜いて作ろうとしたが、結果は失敗作であり(右図 : BONSAI/西宮市大谷記念美術館、1985)、銅線の松葉を束ねた鉄線の小枝を鉄の枝に溶接する手法へと「転向」したのだが、それは少なくとも中ハシ自身にとって「彫刻」の否定にほかならなかった(左図 : Otomi/「松のある風景」/東京、村松画廊、1990)。(8) にもかかわらず、いや、だからこそ、彼は、彫刻的ならざる手法を用いながら「彫刻」を目指すことになっていくのである。
たとえば、近作の一対の昭和天皇像「あなたの時代」にしても、それがブロンズの鋳造という伝統的手法を取りながら、一方に金箔が施されることで、同じ型から鋳抜かれた二体の彫刻は、その表面の処理の違いによってまったく違った見え方を呈することになる。そして、それを観る者は、彫刻がもつはずであった「ボリューム」や「深み」から、むしろその「表層」へと引き戻されてしまうのである。この「あなたの時代」もまた、彫刻的でありながら彫刻的でない彫刻だといえよう。
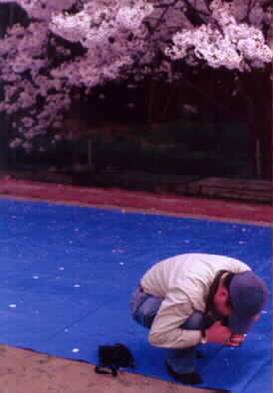
ブロンズへの着彩は、80年代半ばの"Dog Nights"などにもすでに見られるが(9)、中ハシが写真という手法を用いるようになったのは、90年代の半ばからであり、写真のジクソーパズルをはじめた作品としては「4月5日」がある(左図 : 4月5日/「アート遊園地」/伊丹市美術館、1998、撮影風景)(10)。中ハシは、桜の木の下にブルーシートを敷き、その上に舞い散った花弁を、夜明けから日没まで13時間かけて、東から西に向かって連続的に撮影し、そして、現像した写真を美術館で公開制作しながら10日間にわたってセロファンテープでつなぎ合わせたのである。中ハシは後に、「カメラが上下に動いて、大きくなったり小さくなったりするんだよ」と語っているが、撮影のときには、被写体の地面との距離を均一に保つことはできないし、手ぶれや撮り落しなどが生じるのも避けられない。その結果、写真をうまくつなぎ合わせようとしても、けっしてきちんと重なり合わず、出来上がった作品もけっして平面的なものとはならない。「4月5日」では、作品はいかにも平面的に床に据え置かれていたが、米軍硫黄島上陸の日に当たる2月19日に、沖縄で緋寒桜(ひがんざくら)の花が落ちた地面を撮影した「2月19日」、また、かつてダグラス・マッカーサーが連合軍総司令部を設置した建物がブリスベーンに現存しているが、その建物正面を撮影した「9月2日」などでは、写真は床にベッタリ並べられるのではなく、一枚一枚、壁にセロファンテープでぶら下げられるようになる(11)。その結果、写真は波打ったうねりを示し、そこには平面的ではない不思議な「深み」が立ち現われることになるのである。中ハシは、「4月5日」の制作を振り返りながら、方向や位置の感覚を奪ってしまう近接撮影のときに抱いた、まるで盲目となって「ブルーシートに眼球を触れながら手探りしている」ような感覚、そして、撮影時の記憶を辿りつつ、ジクソーパズルのように写真をつないでいたときに抱いた「自分の視線を直に触れている」ような感覚、そうした「二度の視覚と触覚の逆転」に言及していたが(12)、「4月5日」などの作品は、彫刻的ではない写真の表面性をもちながらも、視覚的というよりはむしろ触覚的なものとして、同時にきわめて彫刻的な作品でもあったのである(13)。
──そして、"ZERO"。
プラモデルを接写し、プリントされた写真をつなぎ合わせて制作される"ZERO"が、「4月5日」などの作品のさらなる展開であることは、もはや明らかであろう。
ところで、中ハシは「問いかけとしての芸術」という言い回しを好んで用いる。たとえば彼は、ブリスベーンでのアーティストトークの際、自分はいかなる戦争も肯定できないが、ドグマティックな反戦論を唱えるつもりもないと述べ、「芸術家に求められている大切なことは、裁くことではなく、その反対に様々な視点で多くの人たちに問いかけることなのです」と語っていた(14)。この言葉からすれば、彼にとって"ZERO Project"とは、「戦争」について何らかの政治的メッセージを伝えるためというよりは、むしろ人々が「戦争」についてあらためて考え、語り合う、そうした「場」を作るためのものであったといえよう。
しかし、1998年に中ハシがはじめて制作した"ZERO"は、いわば一般名詞としての「零戦」にすぎず、展示された場所も「零戦」あるいは「戦争」との具体的関連をもたない大阪のある美術館であった。そして、彼自身述懐しているように、そこでは、「戦前派」、「戦後派」、「戦無派」が、実体験としての「戦争」やプラモデルの「戦争」といったそれぞれ別の思いに浸り、互いの間で「戦争」への問いが深められたとも思われない。それは、そこが非-政治的な場とされる「美術館」であり、彼らがそこを訪れたただの「観客」にすぎなかったことにもよるのだろうが、同時に、そこにあったのが具体性を欠いた匿名の「零戦」にすぎなかったからではなかろうか。どのように観ることをも許されてしまう曖昧なそのありかたのせいで、人々はそれぞれ気儘な思いに耽ることになったのだろう。
ところが、中ハシの"ZERO Project"は、1998年の大阪から2002年のカウラに至るまで、度を重ねるごとに次第にそのかたちを変え、彼のいう「問いかけとしての芸術」の場を作り上げていくことになるし、同時にまた、彼の"ZERO"は、一般名詞から固有名詞へとある具体像を帯びていくことになるのである。

その一つの転機は、中ハシのオーストラリアとの出会いだった。1999年のブリスベーンでの「第3回アジア太平洋現代美術トリエンナーレ」の出品作家として、彼は、かつての「敵国」オーストラリアで"ZERO"をはじめて展示するが、これがその後、ダーウィン、カウラと続くオーストラリアでの展示の端緒となる。そして、ダーウィンとカウラでのプロジェクトは、中ハシにとって南忠男こと豊島一(とよしまはじめ)という一人の死者との出会いの旅ともなったのである。
かつて軍港であったダーウィンは、1942年2月19日、日本海軍機動部隊の爆撃機、戦闘機188機の攻撃にはじめて曝されたが、以来1943年11月までにダーウィンは64回の爆撃を被り、町は廃墟と化した。"Australia's Pearl Harbor"と呼ばれるその最初の攻撃の際、イースト・ポイントの砲台により撃ち落された零戦の操縦士豊島一一等飛行兵は、はじめての日本人捕虜としてカウラ捕虜収容所に収容されていたが、彼の突撃ラッパを合図に1,104名の日本人捕虜が決起した、1944年8月5日の絶望的な集団蜂起の際、負傷、その場で自決した。"Mass Breakout at Cowra"と呼ばれるこの事件での死亡者はオーストラリア人4名を含み235名、負傷者は107名にのぼった。死者たちは、カウラの日本人戦争墓地に当時の偽名のまま葬られているが、豊島一の偽名は「南忠男」であった。ちなみに、ダーウィンのオーストラリア航空博物館には、メルヴィル島に不時着した豊島の愛機の残骸が1977年回収され、展示されている(15)。
2000年のダーウィンの"ZERO Project"は、これらの事実を踏まえてのものとなった。彼が作った"ZERO"はもはや匿名の零戦ではなく、機体番号BII-124という豊島の愛機であり、しかもオーストラリア航空博物館のその残骸のかたわらで中ハシは"ZERO"の制作、展示を行なったのである。さらに展示終了後、"ZERO"は、"Australia's Pearl Harbor"の際に爆撃を受けた場所に建つノーザン・テリトリー準州議事堂へ運ばれてあらためて展示されたのち、 8月15日、豊島機を撃ち落した砲台跡があるイースト・ポイントへ、中ハシと市民約150名によって運ばれ、焼却された(上図 : Burning ZERO Project in Darwin──Performance view at East Point, Darwin, on 15th August, 2000)。

また、2001年のカウラでの"On the Day Project"の際には、中ハシは、集団蜂起の日に当たる8月5日、決起した下士官兵が収容されていたカウラ捕虜収容所Bコンパウンド跡地の地面に、死亡した231人の捕虜番号を記したユーカリの葉を散らし、それを撮影。そして、カウラギャラリーにおいて、ボランティアの協力を得て、豊島の零戦とともに、Bコンパウンドの地面をも再現、展示した。さらにその後、彼は市民とともに"ZERO"を収容所入口まで運び、焼却したのである(左図 : ZERO#BⅡ-124/"On the Day"/Cawra Gallery, Cawra, 2002。下図 : On 5th August/"On the Day"/ Cawra Gallery, Cawra, 2002)。
これらのプロジェクトがそれまでの"ZERO Project"と異なるのは、まず、それらが、歴史的事実と結びついた日や場所で行なわれたことであろう。中ハシは、"Australia's Pearl Harbor"と"Mass Breakout at Cowra"の地で、終戦記念日の8月15日や暴動勃発の8月5日に日程を合わせながら、それらの場所にともに関わる豊島一の零戦を展示したのだから──。こうして、これらの地での彼の"ZERO"による問いかけの対象は、もはや漠然とした「戦争」一般などに収まり切れない具体性を帯びることになったのである。

ところで、かつての「敵地」であり、在郷軍人会のメンバーなど戦争経験者も少なからず生存するオーストラリアでのプロジェクトは、意外なことに、在郷軍人会やベトナム戦争帰還兵の会のメンバーを含め、多くの人々の協力やボランティア活動によって支えられることになる。とりわけカウラでは、"ZERO"を焼却地まで運ぶパレードだけでなく、写真の接合作業にもボランティアがはじめて積極的に参加し、そこでさまざまな交流が生まれることになった。その結果、人口7,000の町カウラで、口づてに噂が広まり、戦争体験者である祖父母の代からその孫の代まで、実に2,000人の人々がギャラリーを訪れたのである。──中ハシの"ZERO"は、オーストラリアの地で、アドルノのいわゆる「芸術作品の墓場」としての「美術館」から逃れ出て、それを観る者たちとの生き生きとした関わりを回復する「問いかけとしての芸術」というありかたを実現しうる場を見出したといえよう。ダーウィンやカウラで明らかになったことは、中ハシの"ZERO"が、出来上がった「作品」というよりむしろ撮影から焼却までの「過程」であり、その「過程」での人々との関わりだということではなかろうか。
大阪や西宮の地でのかつての"ZERO Project"の際、「戦争の記憶」を"ZERO"として形象化することへの危惧の念を私は抱いていた。それは、「神風特攻」を暗示させるそのひしゃげた残骸のような姿が、そこで思い起こされる戦死者たちの像を、特攻や玉砕で「水漬(みづ)く屍、草生(くさむ)す屍」となった「日本人」だけに排他的に限定してしまい、「戦争の記憶」をナショナルな記憶へと回収してしまうのではないのか、という危惧であった(16)。しかし、オーストラリアでのプロジェクトは、そうした危惧が杞憂(きゆう)であることを示した。"Australia's Pearl Harbor"や"Mass Breakout at Cowra"、あるいは、南忠男こと豊島一をめぐって、プロジェクトの過程にさまざまなかたちで関わった人々の間で、目撃者も含め、かつての敵味方、民族や世代の違いを超えて交わされた言葉は、ナショナルな記憶へと回収されようのない多声性(ポリフォニー)を身に帯び、中ハシの"ZERO"は、そこで新たに語り出され、さらに語り継がれていくであろう「戦争の記憶」の"ゼロ"、原点になりえたかと思われるのである。
中ハシの"ZERO Project"はさらに続けられていく。カウラで一つの結節点を見出した彼のゼロの旅程は、今後どこへと向かっていくのだろうか。
(1)椹木野衣『「爆心地」の芸術』晶文社、2002年、382頁。
(2)1998年大阪府立現代美術センターで開かれた中ハシのはじめての"ZERO"展の際に、1月10日同センターで行われた中ハシと中井康之(西宮市大谷記念美術館学芸員(当時))との対談「作家と語る」。
(3)同上。ちなみに、中ハシは当時、"![]() "という絵文字をこの作品のタイトルとしていた。
"という絵文字をこの作品のタイトルとしていた。
(4)藤津亮太「スーパーフラット戦記」、『美術手帖』2001年4月号、187頁。
(5)ハナ肇、植木均らのコミック・バンド「クレージー・キャッツ」全盛期の1962年封切りの東宝映画、古澤憲吾監督『ニッポン無責任時代』の主題歌。作詞、青島幸男、作曲、萩原哲晶。
(6)中井康之との対談「作家と語る」。
(7)「あなたの時代──Your Majesty's Reign」と題して、2001年に中ハシの二体の昭和天皇像が展示されたのは、米子、やの美術ギャラリー、および、大阪、児玉画廊においてであった。
(8)中ハシの蝋型鋳造による松の作品としては1985年の"BONSAI"があり、銅線や鉄線を用いた作品には1990年の"Otomi"などがある。当時の彼は、剪定(せんてい)され畸形化された"fake"としての松を作品化することで、いわゆる「日本の自然」が恣意的に作り上げられた「人為としての自然」にすぎないことを戯画化して示そうとしていた。
(9)"Dog Night"は、1986年、東京、東芝ビルで開かれた「芝浦アートフェスティバル Party-1 」に出品された。
(10)「4月5日」の公開制作と展示が行われたのは、1998年の伊丹市美術館における中ハシ克シゲ、太田三郎、藤本由紀夫の3人展、「アート遊園地」に際してであった。
(11)「2月19日」、「9月2日」はともに、2000年に西宮市大谷記念美術館で開かれた「中ハシ克シゲ展──あなたの時代」で展示された。
(12)中ハシ克シゲ「見ることと触れること」、『アート遊園地』図録、伊丹市立美術館、1998年。
(13)「4月5日」などこれらの作品は、夜明けから日暮れまでの間に撮影されたため、左右は露出不足でかなり暗く、中央はいささか露出オーバーぎみとなっている。これらの作品は、彫刻にはない写真の「時間性」、「瞬間性」をも色濃く身に帯びているのである。
(14)中ハシ克シゲ「第3回アジア太平洋現代美術トリエンナーレでの中ハシ克シゲのアーティストトーク(1999年9月9日)」、『中ハシ克シゲ展──あなたの時代』図録、西宮市大谷記念美術館、2000年。
(15)この歴史的経緯については、中野不二男『カウラの突撃ラッパ──零戦パイロットはなぜ死んだか』、文藝春秋社、1984年、を参照されたい。
(16)そうした危惧の念を、篠雅廣も表明していた。彼はこう述べている。「" ![]() (ゼロ)"は、搭乗員の悲しみ、見送った人々の悲しみを伝えてくれるでしょうが、その機関砲から飛び出す銃弾に倒れた幾千倍のひとびとの悲しみを伝えてくれているのでしょうか」。(篠雅廣「Nowhere man, nowhere land」、『中ハシ克シゲ展──あなたの時代』図録、西宮市大谷記念美術館、2000年)
(ゼロ)"は、搭乗員の悲しみ、見送った人々の悲しみを伝えてくれるでしょうが、その機関砲から飛び出す銃弾に倒れた幾千倍のひとびとの悲しみを伝えてくれているのでしょうか」。(篠雅廣「Nowhere man, nowhere land」、『中ハシ克シゲ展──あなたの時代』図録、西宮市大谷記念美術館、2000年)